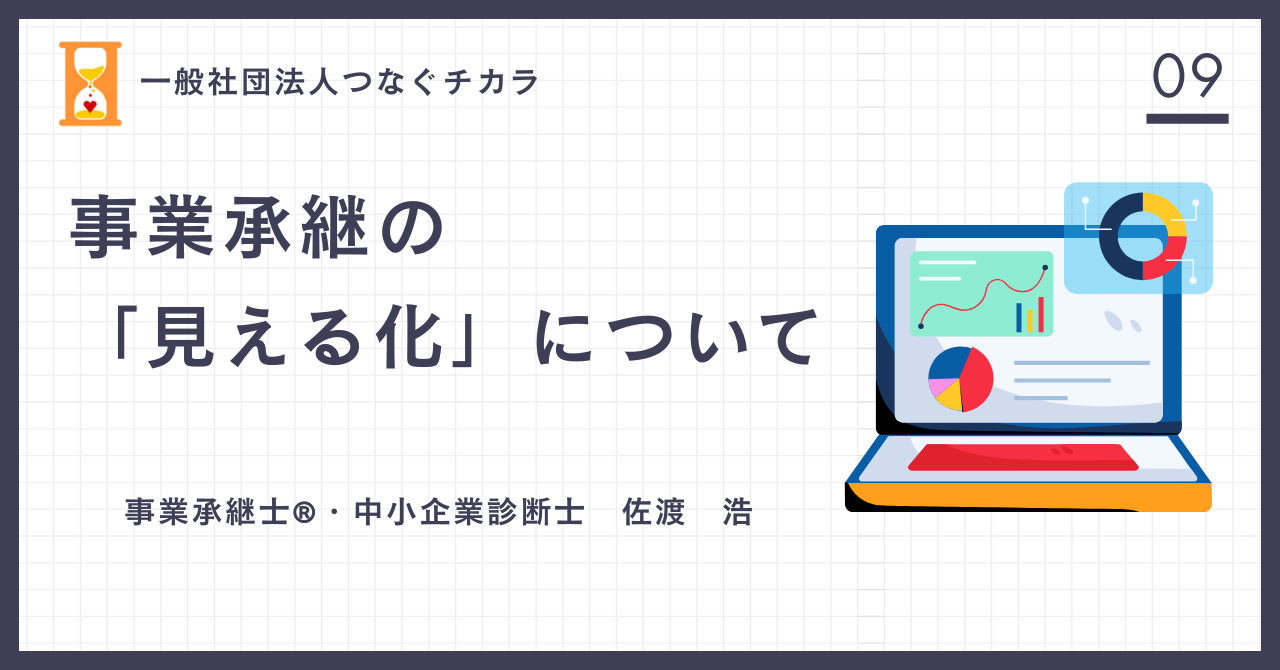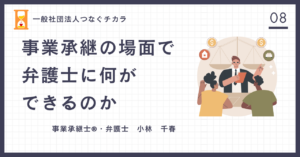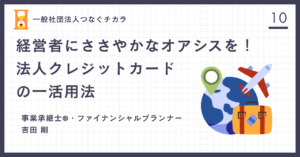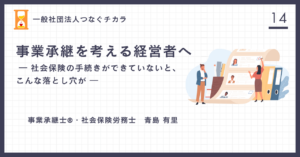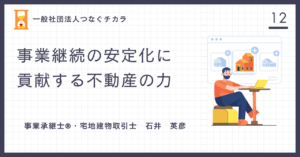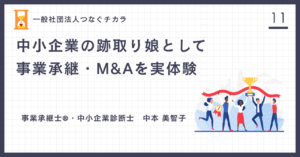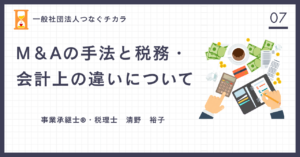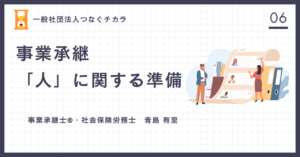はじめに:事業承継の「見える化」──安心できる未来のために
事業承継は「経営権と財産の引継ぎ」や「税金や法的手続きの整理」だけの話ではありません。社長ご自身の胸に抱いてきた想いや会社の誇りを未来へつなぐ大切な行為です。そこで大切なのが「見える化」です。これは、社長の心の中の熱い想いや信念を図や言葉にして整理し、社員や後継者、家族と共有できるようにすることを意味します。
これによって、「なんとなく不安な気持ち」を「具体的な見える課題」に変え、承継への道筋を明確にすることができます。さらに、後継者に安心感を与え、組織全体で応援したいという気持ちが芽生えるのです。ここからが安心して未来に踏み出す第一歩となります。
「不安」を「見える」にする意味
漠然とした不安を具体化する
「いつか来るその日」に漠然とした不安を抱えるのは当然のことです。しかしその不安が不安のままでは、最初の一歩は踏み出せません。「見える化」はその不安を具体的な課題として言語化・数値化する営みです。
- 現状整理:現状の借入金や不動産、設備リストを紙に書き出してみる
- 想いの棚卸し:「会社をこうしたい」「働く人へこうしたい」という社長の想いを言葉にまとめる
こうした作業を通じて、「わかってはいたけれどあえて見ないふりをしていた課題」を前に出していきます。
安心感の生まれる仕組み
具体化された課題は「取組みへの手がかり」に変わります。「まずは顧問税理士の先生に相談しよう」、「事業承継の専門家に会ってみよう」など、行動へのステップが明確になります。その積み重ねが、社長ご自身に「安心して先を考えられる」心の余裕をもたらします。
見える化の3つの柱
ここでは「事業価値」、「想い」、「対話」という3つの観点を「見える化」するポイントを解説します。
事業価値の見える化
企業の価値は数字だけでは表現できません。当然に手元の現金や利益は必要ですが、技術力、ブランド、社員が持つ信頼、顧客や地域とのつながりなど、これら無形の資産をどう見える形にするかが事業承継にあたっては特に重要です。
- キャッシュフローと利益予測
過去のキャッシュフロー実績をもとに「将来の利益予測」を図表化します。これにより視覚的に未来のお金の流れが見えることで、経営計画として説得力・納得感が増します。 - 無形資産シートの作成
技術やブランド力など、「ヒト・モノ・カネ」以外の価値について、チェックリストを用意して振り返ります。たとえば社長が長年育ててきた職人の技術を「どこまで独自か」、「社内に継承されているか」など具体的に項目化します。
想いの見える化
社長がこれまで大切にしてきた経営や会社の文化は、実は社内で共有されていなかったということも往々にしてあり得ます。個人の想いは誰もが納得する形ではなかなか共有されにくいものです。想いをきちんと言葉にすることで、“誰にでも伝わる資産”に変えることができます。具体的には次のプロセスを通じて「社長の想いの見える化」を行います。
- 社長インタビュー+物語構成
事業承継の専門家が社長ご自身の言葉を取材し、それをストーリーとしてまとめます。「自分の出発点」、「困難をどう乗り越えたか」、「これからの会社に何を残したいか」などを語っていただくことで関係者に共感と納得感を醸成します。 - 数値・歴史・想いの三位一体スライド化
単に数字やグラフがあるだけの資料では心に響きません。そこに創業からの歩み、節目のエピソード、社長のひと言を加えることで、資料全体にストーリーが生まれ、関係者の感情にも訴えかけます。
対話の見える化―ツールの活用
いくら素晴らしい資料があっても、社長一人の想いだけでは承継はうまく進みません。後継者をはじめ、幹部・社員も巻き込むことが大切です。
- 価値観の共有
家族会議を開催し、「何を大切にしたいか」、「どういう会社でありたいか」を参加者全員に書いてもらい、共通点やズレを可視化します。考えを書いたポストイットを貼るスタイルだと対話も自然に弾みます。 - 将来について後継者と認識合わせ
「5年後、10年後に会社はどうなっていてほしいか」を後継者と一緒に書き出し、ゴールのすり合わせをします。これにより、対話が深まります。
成功を支える3つのポイント
ここで「見える化」成功の要素を整理します。
一人で抱え込まない
社長自身が「全部自分一人で決めなくていい」と気づくことが重要です。最初からすべて完璧に見せようとせず、できるところから始める柔軟性が必要です。
専門家を味方に
数字に強い税理士、自社株式や事業用資産の承継に強い弁護士、経営全般を俯瞰し全体を支援できる中小企業診断士などの専門家──それぞれの専門家が関わることで、社長は本来の「経営者の目線」に集中できます。
対話と発信の場を作る
「見える化」は資料作りだけでは終わりません。それを「誰と共有し、どう使うか」が肝要です。社員や家族との対話、後継者への語りかけによって想いが浸透していきます。
「見える化」によって期待される5つの成果
「見える化」によって得られる成果としては以下のようなものが考えられます。
- 社長の安心感:「言葉にできたことで、ようやく“継がせていい”という気持ちになれる」
- 後継者の納得感:「社長の考えが具体的にわかって、自信を持って一歩踏み出せる」
- 社員の自発的な協力:「会社の未来を自分たちも考えるようになる」
- 関係者からの信頼向上:金融機関や取引先に対して、「継続性のある会社」として印象がアップする
- 承継の円滑化:感情のこじれが起きず、スムーズな引き継ぎが可能になる
気をつけるべき「見える化」の落とし穴
数字だけに偏る
「見える化」=経営指標、と思ってしまうと「心」が抜けてしまいます。会社の“魂”を伝えるのは、数字と想いの両輪です。
後継者の理解を置き去りにする
特に自分の子供を後継者として考えている場合は、「まだ若いからわからないだろう」と対話を後回しにしてはいけません。実際に言葉を交わすことで、お互いに理解が深まります。
無理に急ぎすぎる
「見える化」は「事業承継を完成させること」ではありません。「対話のきっかけを作ること」そして事業承継を機に「会社の磨き上げを図ること」が本質です。時間をかけても、一つ一つ丁寧に取り組むことが大切です。
専門家と進める際のチェックポイント
□ 数字面は顧問税理士等の助けを借りているか
□ 想いの整理に寄り添ってくれる相手がいるか
□ 後継者や社員と共有する“場”を作っているか
□ 必要に応じて外部の支援制度(補助金・支援機関)を調べているか
□ 「自分だけで全部進めようとしていないか」と時々振り返っているか
今すぐできる!小さな見える化アクション3選
アクション1:A4一枚で「私の想い」を整理
「この会社をどうしてつくったか」、「これから大切にしたいこと」などをA4一枚に書いてみましょう。誰に見せなくてもかまいません。まずはご自身のための整理です。
アクション2:「見える化チェック」簡易セルフ診断
- 自分の会社の強みを3つ言えますか?
- 後継者にそれを伝えたことはありますか?
- 誰かに「うちの将来」を話したことはありますか?
Yesの数が多いほど、見える化の準備が進んでいるサインです。
アクション3:「専門家にひと声かけてみる」
補助金や支援制度も活用しながら、伴走してくれる相手を見つけてみましょう。公的支援機関でも無料相談があることが多いので、気軽に一歩踏み出してみてください。
まとめ
事業承継の「見える化」は、決して難しいことではありません。
紙に想いを書き出すこと、数字をまとめること、後継者とゆっくり話すこと。
その一つ一つが、会社の未来を形づくる大切な一歩です。
70歳を過ぎても、まだ会社のことを考えてしまう──それは社長が人生をかけて会社を築いた証です。
だからこそ、その想いを次の世代へ丁寧に届ける価値があるのです。
「見える化」は、会社にとっても社長にとっても“心の整理”の時間です。
今ここから、小さく始めてみませんか?
事業承継士、中小企業診断士: 佐渡 浩