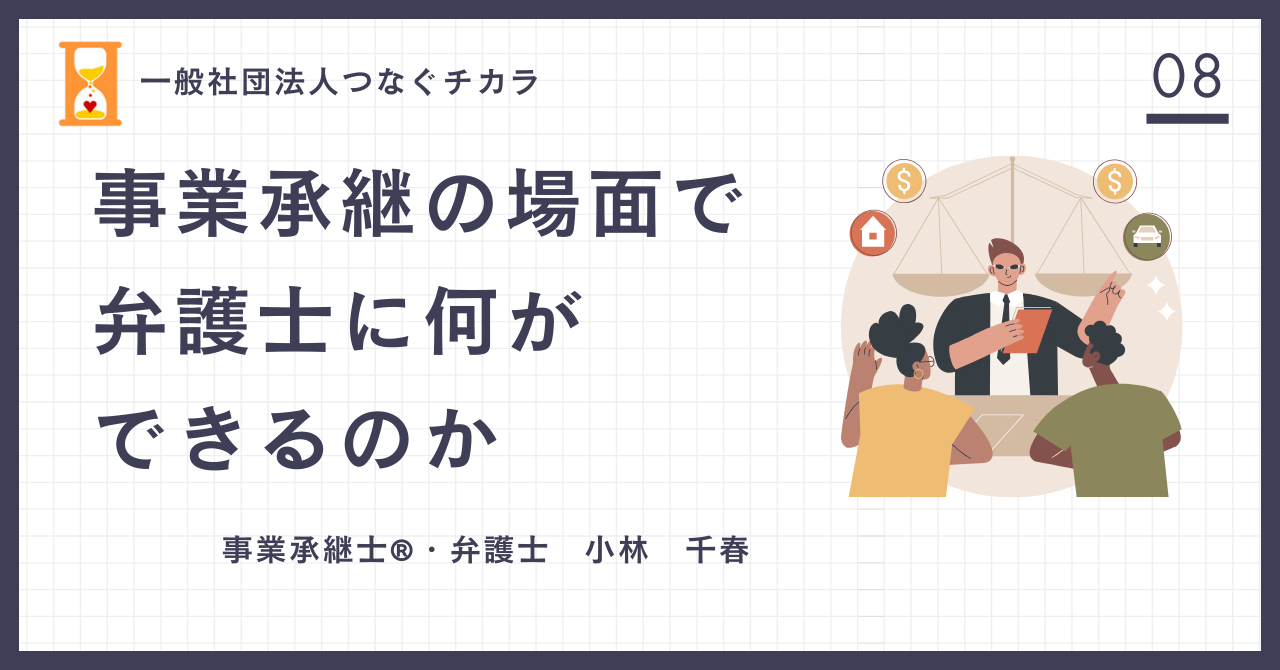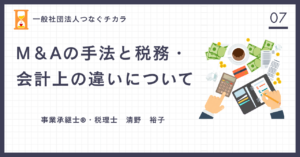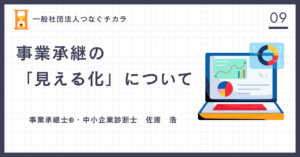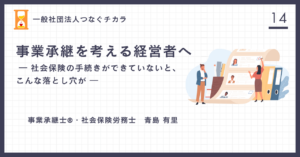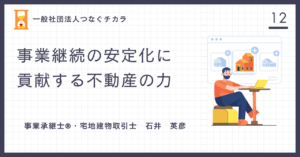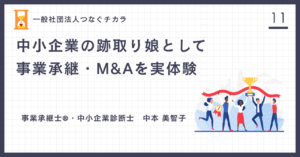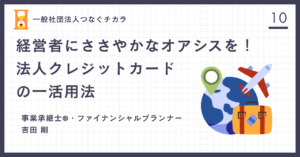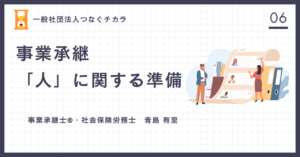事業承継は、異論あるかもしれませんが、会社支配権・会社経営権の承継です。
会社支配権の承継とは、すなわち株式を誰が譲り受けるのかという話です。
会社経営権の承継とは、すなわち誰が社長を引き継ぐのかという話です。
子に会社を継がせようと思い立った場合に思いつくのは、やはり株式をどうやって子に渡すのかということです。
暦年贈与でこまめに株式を子に移し、会社が大きな欠損を出して一時的に債務超過になった際に株式をまとめて贈与する、なんて話をよく耳にします。
あるいは、会社の内部留保が大きくて(これはとっても良いことだと思います。)どう頑張ってもたくさんの株式を贈与できない場合、様々な仕組みを用いて株価を下げた上で子に株式を贈与したり、子が株を購入したりするといったことも耳にします。
こういう場面では、「株価」すなわち金額の問題なので、弁護士が関与することはあまりありません。
誰を社長に据えるのかという場面では、さらに法律が関与する側面は薄れます。この場面では、「社長」という肩書よりも、子が従業員にリーダーとして認められ、社内を掌握していくということが大事で、その過程で悪戦苦闘することで真のリーダーが育まれる、みたいな感じではなかろうかと思います。
ですので、弁護士がお手伝いする場面とは言い難いところがあります。
「そしたら、事業承継では弁護士はいらないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、デューディリジェンスとか、100%株主ではない場合の株式の集約とか、事業承継の前さばきでお手伝いする場面はあったりしますし、何と言っても事業承継が無事にできても、実は将来に禍根が残っていたということもあります。顕著なのは遺留分です。
弁護士は、法的紛争の解決に関与することが多いのですが、法的紛争に関与していると、「将来のきな臭さ」を感じ取ることがあります。この「将来のきな臭さ」を取り除くのが、いわゆる「予防法務」というもので、これまで述べてきた中では遺留分で紛争にならないよう対策を講じておこうというのも一つの関与場面です。
「保険」や「セキュリティ」と同じで、事業承継の場面でも、弁護士は、将来のリスクに備える場面でお手伝いすることができます。
「将来のリスク? そんなもの、起こらないかもしれないじゃないか」と思われた方。ごもっともですが、いわば、無保険で自動車に乗るのと同じ状態です。企業経営は、普通にしていても色々なトラブルに見舞われますが、深刻なトラブルに遭遇しないよう、事業承継の場面でも弁護士を上手に使いこなしていただけたらと思います。
事業承継士®・弁護士 小林 千春