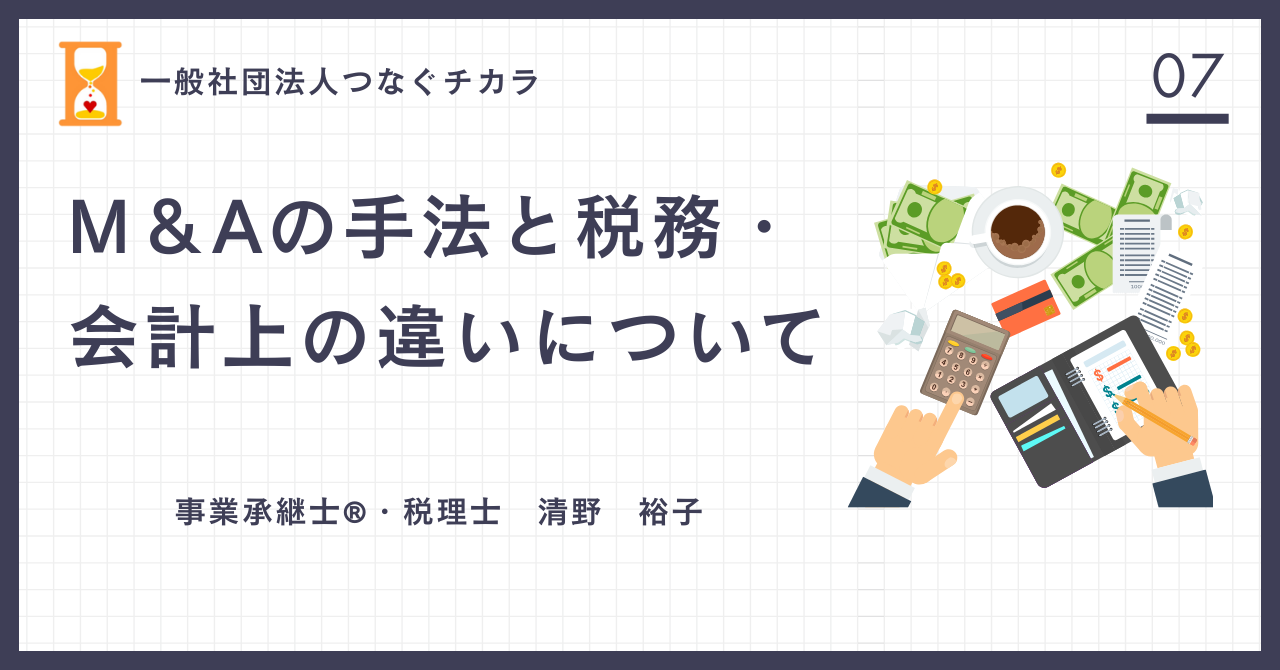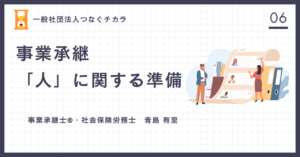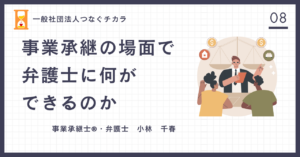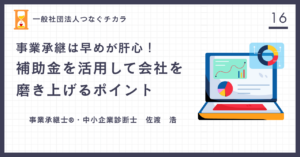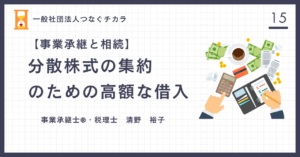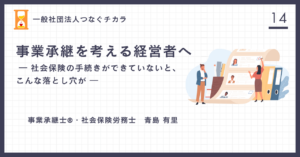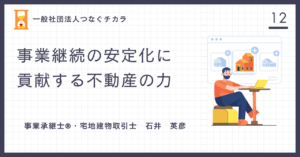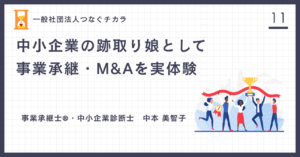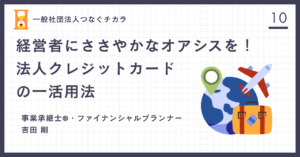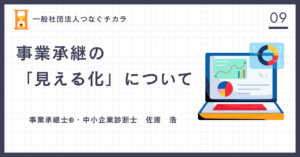中小企業におけるM&Aの現状
中小企業庁は、中小企業のM&Aを手掛けるアドバイザー資格を2026年度にも創設する。
中小企業庁が2024年6月に発表した『事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について』によると、中小企業のM&Aの実績は、2014年362件、2022年は5,717件と10年前に比べて約16倍と飛躍的に伸びている。そして興味深いのは、その内訳である。事業承継・引継ぎ支援センターを通じて実施されたM&Aは、2014年が102件、2022年は1,681件と約16倍。民間のM&A支援機関を通じた件数は2014年が102件。2022年は4,036件と約40倍となっている。但しこの民間の支援機関の件数はあくまでM&A登録支援制度実績報告の成約件数を基にして算出された件数であるため、実際にはもっと多いものと推察される。2024年にNHKニュースで取り上げられた「吸血型M&A」という言葉は衝撃的で、これらの仲介業者が実施した件数は上記件数には含まれていない。国が重すぎる腰をあげたのは、このような悪質な仲介業者が増加の一途をたどっているからに他ならず、あまりにも遅すぎたのではないかと思っているのは筆者だけではないと思う。
さて、M&Aとは、「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」を略した言葉で、この用語はあくまで法律用語ではなく経済用語からきている。企業や事業の経営権を移転し事業を拡大するための方法を指し、その方法はそれぞれの目的や実態に伴いさまざまである。
M&Aの手法
中小企業の場合、主に次の5種類を用いられることが多いのではないだろうか。その中でもよく耳にされる「株式譲渡」「事業譲渡」は、契約に基づく売買である。「会社分割」「合併」「株式交換」は、あくまで会社法上の組織再編というくくりになる。後者の組織再編は、債権者や株主等利害関係者に影響があることから、法的手続きを必要とし官報による公告等が必要となるため、ハードルが高く、専門家のサポートが必須である。但し、一定の要件を満たすと税法上の優遇を受けられる可能性がある。
M&Aの手法と税務・会計上の違いについて
今回は、一般的に用いられることが多い「株式譲渡」と「事業譲渡」についてわかり易くお伝えする。同じ〇〇譲渡だが、全く異なるものである。「誰が」「何を売却」「結果どうしたい」。が最も大きく異なる。
株式譲渡
〇誰が…対象会社の株主(中小企業では個人のことが多い)
〇何を売却する…保有する株式を売却
〇結果どうしたい…経営権を移転する(対象会社はなくなる)
事業譲渡
〇誰が…対象会社
〇何を売却する…一部又は全部の事業(資産・負債・契約等)
〇結果どうしたい…対象会社から一部又は全部の事業を切り離す(対象会社は残る)
株式譲渡のデメリットとして言われる「滞在債務も引き継ぐことになる。」とは、株式(経営権)が移転することにより会社がなくなるため、対象会社の全てを引き継ぐことになる。帳簿に記載されていない従業員への未払残業代も知らない間に引き継ぐ可能性がある。ということになる。
株式譲渡から説明すると、買い手である法人の会計処理は至ってシンプルで、「関係会社株式」として取得価額が資産計上されるのみである。こちらは営業権等と異なり償却できるものではない。消費税の仕入税額控除の対象とはならない。
売り手側は、先ほどの「誰が」に該当するが、中小企業は個人(=代表取締役)が株主となっているケースが多い。適用される税法は、所得税(復興所得税含む)と個人住民税である。譲渡益に対して20.315%の課税(所得税(復興所得税含む)+住民税)で完結する。消費税の論点が発生しないことは大きなメリットである。
では、事業譲渡はどうか。
基本的に登場人物である売り手、買い手ともに法人であるため、適用される税法は、法人税と消費税の論点が発生する。売り手側は売却する資産ごとの譲渡益に対して、法人税が課税される。また、消費税は、譲渡する課税資産(例えば建物や器具、機械等)と営業権(のれん)について課税されることになる。もう一つ付け加えると、事業を売却することによる譲渡代金は、法人に入ることになる。それを株主や役員に還流させる場合には、配当所得や役員報酬による所得税の論点が発生する。売り手側の税負担は大きくなる。
買い手側の処理は、取得する資産・負債が計上されるのと同時に、営業権(のれん)が資産として計上される。こちらは原則5年で償却が可能となる。
消費税は、業種にもよるが、原則、売り手側で課税処理されたものが仕入税額控除の対象となる。
事業譲渡の場合、買い手側が考慮しておく必要のある税金がもう1種類ある。「不動産取得税、登録免許税」である。譲渡資産に土地、建物が含まれている場合には、こちらにも留意が必要である。
株式譲渡と事業譲渡が活用されるケースの違いについて
株式譲渡は、一般的によく使われる。というのも、まず所要時間がそこまでかからず、負担が少ないことが大きい。税負担もシンプルで、譲渡代金が株主(本来売却したいと思っている経営者)に入ってくることも大きいと言える。飲食店や建設業、不動産業等は、許認可の継続性についても考慮が必要となるが、原則、変更届出書(代表者や本店住所等)を提出することで完了する。
事業譲渡は、滞在債務を切り離したい場合や事業再生の場合に使われることが多いが、所要時間がかかること。買い手、売り手ともに負担が大きいことに理解が必要である。「何を売却する。」で記載した資産、負債、契約は、個々に判定が必要となる。例えば、従業員との雇用契約についても、個人ごとに再契約が必要となる。また、許認可の継続性については、原則引き継げないため、新規取得が必要となる。営業に空白時間が生じる等のデメリットが発生する可能性がある。
終わりに
今回は、M&Aでよく用いられる手法である「株式譲渡」と「事業譲渡」について、税務上・会計上・ケース別に記載したのだが、何より大切なのは、M&Aを考えるに至った経営者の思いだと思っている。経営者として最終何を求めておられるのか。そのためには、どのような準備をして、どのような方法をとるべきなのか。この判断は、正直、当事者では難しいと思っている。客観的に数字を見、財務・税務・法務・労務の観点から様々な聞き取りをしたうえでないと本当に最適な方法を選択する判断は難しい。そのため、悪質な業者が入る余地が生まれるのだと思う。
私たち「一般社団法人つなぐチカラ」には、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなど事業承継士®がそろっているため、経営者のお気持ちをヒアリングしたうえで、様々な観点から内容を判断し、最終この方法で良かったと思っていただける方法を共に考え、伴奏させていただきたいと思っている。金融機関等で事業承継に係る手数料ビジネスが言われる昨今、私たちは「事業承継を支援したい。」という理念で集まった同志だからである。
どうぞお気軽に、お声がけください。
事業承継士®・税理士 清野 裕子